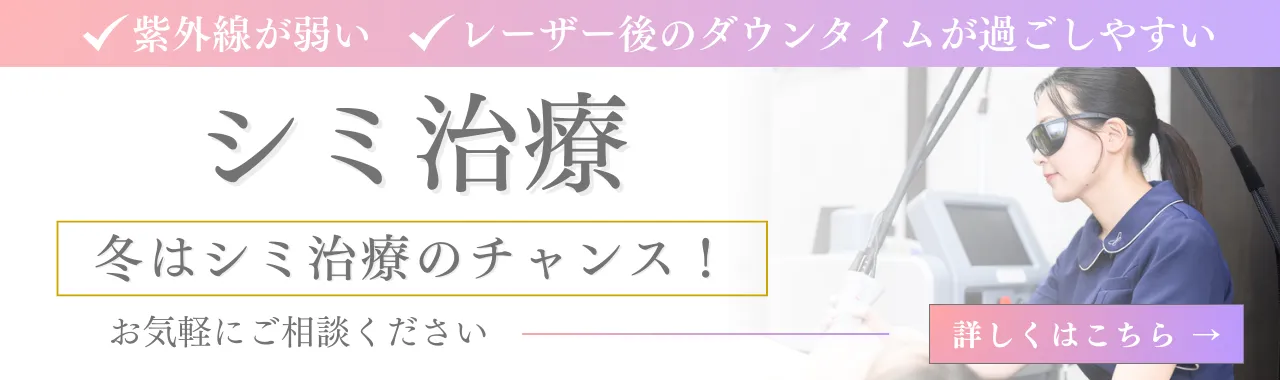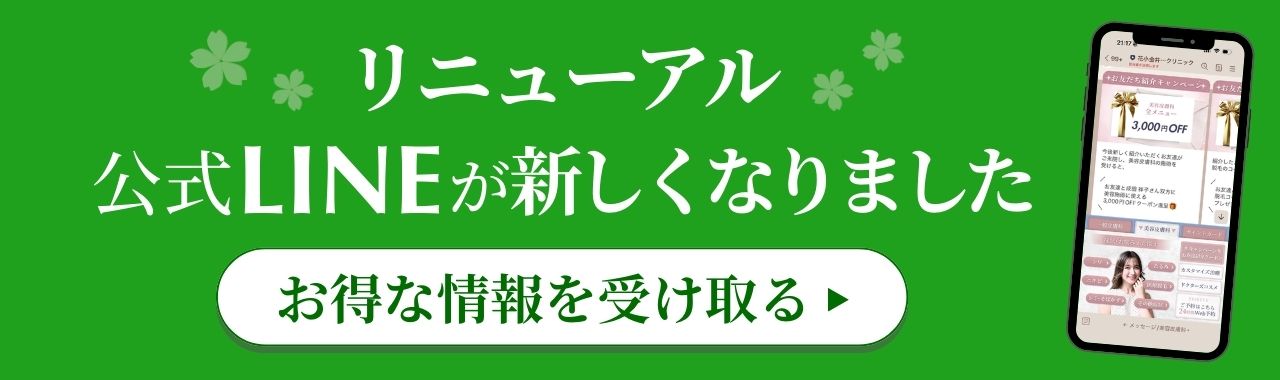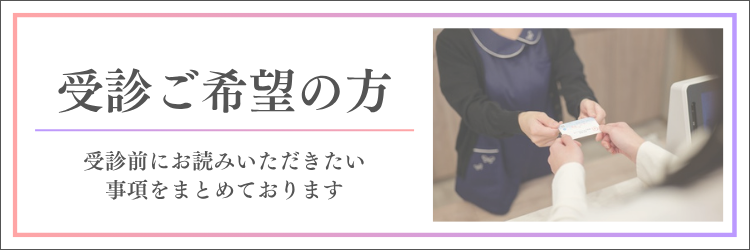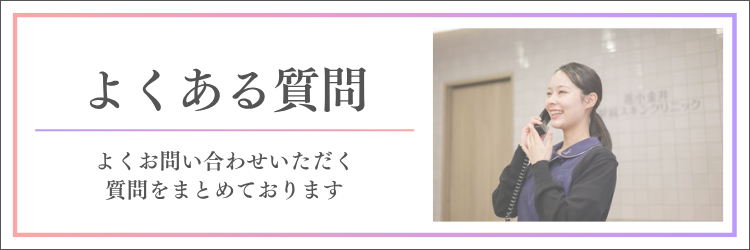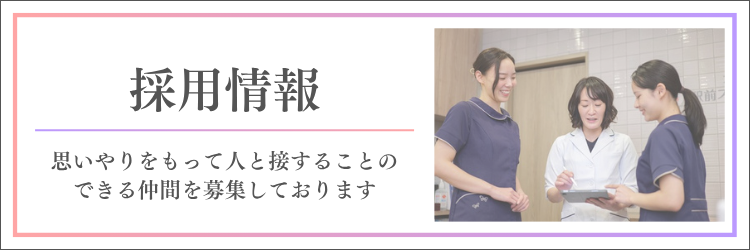とびひについて
とびひは、正式には伝染性膿痂疹(読み方:でんせんせいのうかしん)と呼ばれる、皮膚の細菌感染症です。主に、黄色ブドウ球菌や溶血性連鎖球菌といった細菌が、皮膚の小さな傷口から侵入することで発症します。
とびひは2種類に分類されます。
一つが、みずぶくれができてびらん(皮膚が剥けた状態)を作ることが多い水疱性膿痂疹で、主に黄色ブドウ球菌が原因です。乳幼児や小児に多く、特に初夏から真夏に発症することが多いです。あせもや虫刺されを引っかいたりすることで、感染を起こすことが多いです。
もう一つが、炎症が強くかさぶたが厚くついた、水ぶくれを作らないとびひで、痂皮性膿痂疹と言います。原因菌として、溶連菌の一種のA群β溶血性連鎖球菌です。アトピー性皮膚炎などの慢性湿疹に合併することが多く、季節性はなく、小児より成人に多く発症します。
とびひは、その名の通り、まるで火の粉が飛び火するように、皮膚のあちこちに広がっていくのが特徴です。初期症状としては、水ぶくれや赤い斑点、かゆみなどが現れます。これらの症状を放置すると、水ぶくれが破れてただれたり、かさぶたになったりすることがあります。
適切な治療を行えば比較的早く治りますが、放置すると症状が悪化したり、周囲の人にも感染させてしまう可能性があります。そのため、早期に皮膚科を受診し、適切な治療を受けることが大切です。
とびひの原因
とびひは、主に黄色ブドウ球菌や溶連菌といった細菌が皮膚に感染することで起こります。
これらの細菌は、私たちの身の回りに常在しており、健康な状態であれば、皮膚のバリア機能によって感染を防ぐことができます。しかし、皮膚に傷や湿疹、虫刺されなどがあると、そこから細菌が侵入しやすくなり、とびひを発症することがあります。特に、アトピー性皮膚炎の方は、皮膚のバリア機能が低下しているため、とびひになりやすい傾向があります。
小さな子供は、皮膚が薄く、免疫力も未発達なため、とびひにかかりやすいと言えます。さらに、高温多湿の環境は、細菌の増殖を促すため、夏場にとびひを発症するケースが増加します。
不衛生な環境や、タオルの共用なども、とびひの感染リスクを高める可能性がありますので注意が必要です。
とびひの治療
とびひの治療は、主に抗菌薬を用いて行います。
軽症の場合は、抗菌薬の塗り薬を1日数回患部に塗布します。塗り薬は、患部を清潔にした後、薄く広げるように塗るのがポイントです。患部を触ることで症状が広がるため、できるだけ外用後は清潔なガーゼで保護します。ジュクジュクしている場合は、お風呂の湯船やプールは控えてください。
中等症以上の場合は、塗り薬に加えて、抗菌薬の内服薬を服用します。内服薬は、医師の指示に従って、決められた量を決められた期間、きちんと服用することが重要です。
とびひの治療期間は、症状の程度や治療法によって異なりますが、通常は1~2週間程度で治ります。ただし、治療が遅れたり、適切な治療が行われなかったりすると、症状が悪化したり、治りが遅くなったりすることがあります。また、稀に、とびひが原因で腎臓の病気などの合併症を引き起こす可能性もあるため、早期に医療機関を受診し、適切な治療を受けることが大切です。
とびひの予防・日常のケアについて
とびひは、細菌感染によって引き起こされる病気であるため、予防には、皮膚を清潔に保ち、細菌の感染を防ぐことが重要です。
- こまめな手洗い
外出から帰ったら、食事の前後、トイレの後など、こまめに石鹸で手を洗いましょう。 - 皮膚を清潔に保つ
汗をかいたらシャワーを浴びるなど、皮膚を清潔に保ちましょう。 - 傷口のケア
皮膚に傷がある場合は、すぐに水で洗い流し、清潔なガーゼなどで保護しましょう。 - 爪を短く切る
爪を短く切り、清潔に保つことで、皮膚を傷つけないようにしましょう。 - タオルの共有を避ける
タオルや衣類などを共有することで、とびひが感染する可能性があります。家族間でも、タオルはそれぞれ別に用意しましょう。 - 患部を触らない
とびひを発症している場合は、患部を触らないようにしましょう。また、患部を掻きむしると、症状が悪化したり、他の場所に広がったりする可能性があります。
とびひはうつる?
とびひはうつる病気です。
とびひは、黄色ブドウ球菌や溶連菌といった細菌によって引き起こされる感染症で、接触感染によって人から人へうつります。具体的には、以下のような経路で感染します。
- 患部との直接接触
とびひの患部に直接触れることで、細菌が手に付着し、そこから自分の体や他の人にうつることがあります。症状があるときは、プールや水泳の授業はお休みしてください。 - 患部からの分泌物との接触
とびひの水ぶくれやびらんから出る分泌物には、多くの細菌が含まれています。この分泌物に触れることで、感染する可能性があります。 - 共有物からの感染
タオル、おもちゃ、衣類など、とびひの患者と共有物を介して感染することがあります。
小さな子供は、免疫力が未発達で、衛生観念も十分ではないため、とびひにかかりやすく、また、他の人へうつしてしまう可能性も高くなります。とびひを予防するためには、手洗いをこまめに行い、皮膚を清潔に保つことが重要です。
また、とびひを発症している場合は、患部を触らないようにし、タオルや衣類などを共用しないようにしましょう。さらに、家族など、周囲に人がいる場合は、感染を広げないよう、注意が必要です。
家族や周りの人に、とびひの症状が見られる場合は、接触を避け、早めに皮膚科を受診しましょう。