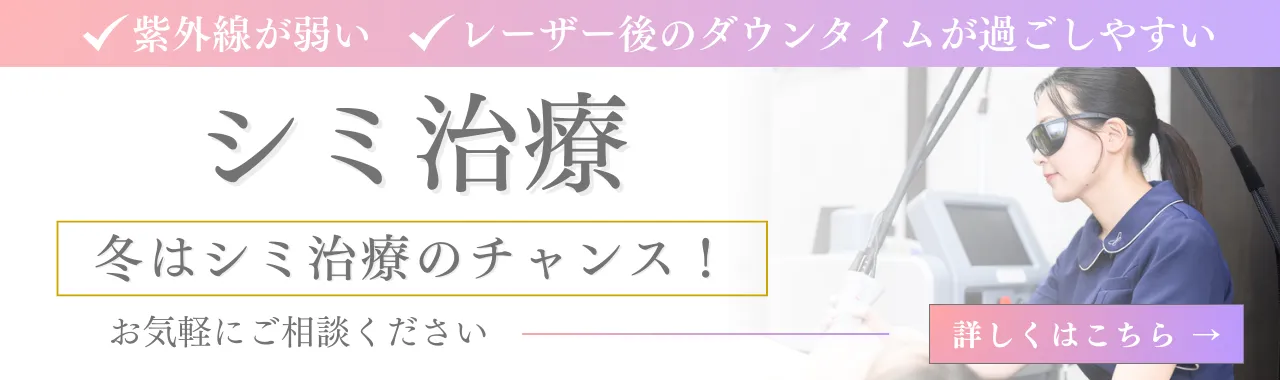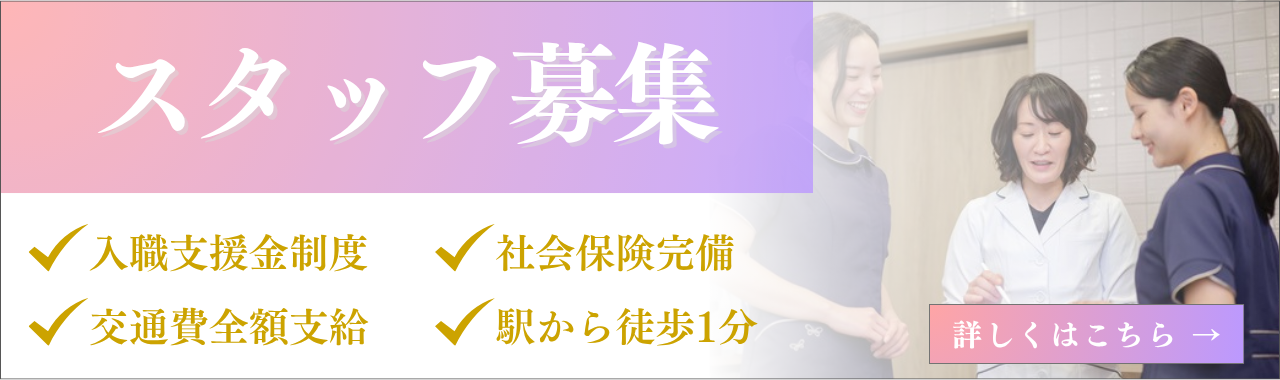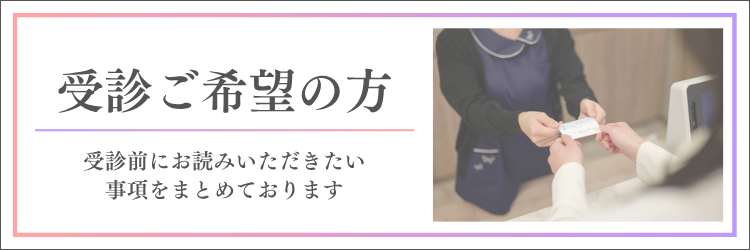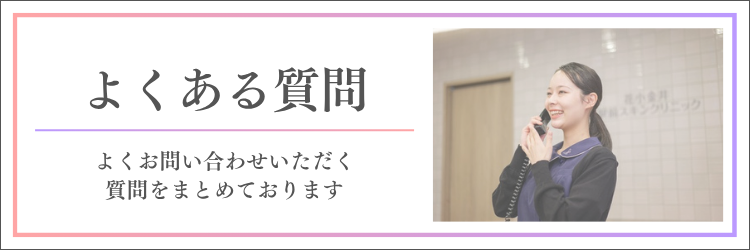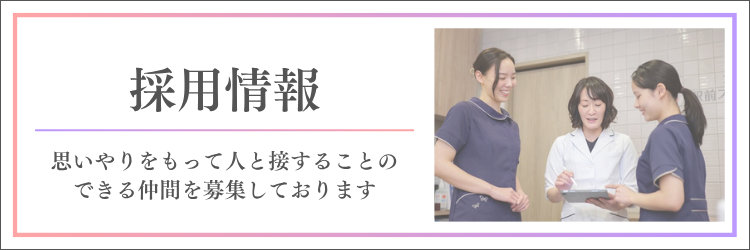水虫について
水虫は、白癬菌というカビ(皮膚糸状菌という真菌)が皮膚に寄生することで起こる感染症です。正式には「足白癬(あしはくせん)」と呼ばれています。
白癬菌は高温多湿の環境を好み、足の裏や指の間などに感染しやすく、かゆみ、赤み、水ぶくれ、皮膚のひび割れなどの症状を引き起こします。
水虫は、感染者から剥がれ落ちた皮膚の角質に触れることで感染します。例えば、共用のバスマットやスリッパ、床などを介して感染することがあります。また、靴の中が蒸れやすい状態や、足の清潔を保てていない場合も感染リスクが高まります。
菌がついたからすぐに水虫に感染するわけではありません。ついた菌のほとんどが容易に脱落し、感染には至りませんが、洗い残しなどから残った菌が、傷ついた角質から入り込み、繁殖しやすい環境にあった場合、感染が起こります。
水虫は放置すると症状が悪化し、周囲の人へ感染させてしまう可能性もありますので、早期に治療を開始することが大切です。
白癬の症例画像
爪白癬(爪の水虫)の症例画像


股部白癬(体部白癬)の症例画像

水虫の原因
水虫は、白癬菌というカビの一種が皮膚に寄生することで起こります。
白癬菌は、高温多湿の環境を好みます。そのため、汗をかきやすい足は、白癬菌にとって絶好の住処となります。
また、皮膚の表面に汗や汚れが残っているアルカリ性の皮膚環境も、白癬菌が繁殖しやすい環境です。
特に、以下の条件が重なると、水虫に感染しやすくなります。
- 足の清潔を保てていない
汗や汚れを放置すると、白癬菌が繁殖しやすくなります。 - 靴の中が蒸れやすい
通気性の悪い靴を長時間履いていると、足が蒸れて白癬菌が繁殖しやすくなります。 - 素足で歩くことが多い
プールや温泉、更衣室など、不特定多数の人が利用する場所で素足で歩くと、白癬菌に感染するリスクが高まります。 - 免疫力が低下している
ストレスや睡眠不足、栄養バランスの乱れなどにより免疫力が低下すると、白癬菌への抵抗力が弱まり、感染しやすくなります。
糖尿病や免疫不全などの持病があり免疫力が弱っている場合も注意が必要です。 - 家族に水虫の方がいる
家族に水虫の方がいる場合、バスマットやスリッパなどを共有することで感染するリスクが高まります。
水虫の治療
水虫の治療期間は、症状の程度や使用する薬剤によって異なりますが、一般的には数週間から数ヶ月かかります。
症状が改善しても、自己判断で治療を中断せずに、医師の指示に従って最後まで治療を続けることが大切です。また、重症化したり、塗り薬で効果が見られない場合は、飲み薬を併用することもあります。
体や股に糸状菌がついた体部白癬や股部白癬では、外用薬を2週間程度きっちりと塗り続ければ完治しますが、足白癬では、一見症状がない部分も含め菌が潜んでいる可能性が高いことや糸状菌が増えやすい環境であることから、4週間から8週間の毎日の外用が必要になります。
塗り薬
抗真菌作用のある塗り薬を使います。
ルリコン、ぺキロン、ラミシールなど多数の種類がありますが、まれに皮膚に合わずにかぶれてしまうこともありますので、医師と相談しながら外用薬を必要な期間毎日継続して治療します。
爪白癬では、以前は外用薬では完治することが難しかったのですが、近年角層に浸透し、高い抗真菌活性をもつクレナフィン爪外用液や、ルコナック爪外用液が開発され、持病などで飲み薬が飲めない爪白癬の方にも、外用薬で治療する方法が増えています。
内服薬
足白癬の中でも、角層が厚くなっている角質増殖型というタイプや、爪に寄生している場合は、外用薬では効果が不十分なことが多く、内服薬による治療を行います。
内服薬には、イトラコナゾール、テルビナフィン、ネイリンがあります。
イトラコナゾールは、1週間内服して3週間休薬する、これを1パスとして、3回繰り返す内服方法です。
テルビナフィンは、1日1回1錠を6か月間内服します。
ネイリンは、1日1回1錠を12週間内服します。
この三種類の中では、ネイリンが一番新しいお薬で、副作用が少なく内服期間も短いため、よく処方されますが、薬価が少し高いお薬になります。どのお薬も、内服中に肝機能障害などの副作用をきたすことがまれにあるため、定期的な採血検査が必要になります。
水虫の予防・日常のケアについて
水虫は、白癬菌が繁殖しやすい環境を作らないようにすることが大切です。毎日の生活の中で、以下の点に注意することで、水虫の予防につながります。
- 足を清潔に保つ
毎日足を洗い、特に指の間は丁寧に洗いましょう。
石鹸をよく泡立てて、優しく洗い、ゴシゴシこすらないようにしましょう。
洗った後は、水分をしっかり拭き取り、乾燥させましょう。 - 足に傷を作らない
白癬が皮膚に侵入し、感染が成立するまで最低24時間かかりますが、足の皮膚に傷がある場合、半分の12時間で感染するというデータもあります。
角質をむしったり、軽石などでこすりすぎて角層に傷があると感染しやすくなりますので、洗いすぎこすりすぎは控えましょう。 - 靴や靴下を清潔に保つ
通気性の良い靴を選び、同じ靴を毎日履かないようにしましょう。
靴下は吸水性の良い素材を選び、毎日交換しましょう。
湿気の多い日は、靴の中に乾燥剤を入れるのも効果的です。 - 共用スリッパやバスマットを使用しない
家族に水虫の方がいる場合は、特に注意が必要です。
共用スリッパやバスマットは使用せず、個別のものを使用しましょう。 - 免疫力を高める
バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動を心がけ、免疫力を高めましょう。
ストレスを溜めないようにすることも大切です。
水虫の薬について
水虫の治療薬は、大きく分けて塗り薬と飲み薬の2種類があります。
塗り薬
塗り薬は、水虫の治療で最も一般的に使用される薬です。患部に直接塗布することで、白癬菌を殺菌したり、炎症やかゆみを抑える効果があります。
塗り薬には、クリームタイプ、軟膏タイプ、液剤タイプなど、様々な種類があります。症状や患部の状態に合わせて、適切な剤形を選択することが重要です。
主な塗り薬の成分としては、以下のものがあります。
- テルビナフィン塩酸塩
真菌の細胞膜の合成を阻害することで、殺菌効果を発揮します。 - ラミシール
テルビナフィン塩酸塩と同じ作用機序を持つ薬剤です。 - ルリコン
真菌の細胞壁の合成を阻害することで、殺菌効果を発揮します。 - サリチル酸
角質を柔らかくすることで、薬剤の浸透を助けます。
飲み薬
塗り薬で効果が見られない場合や、広範囲にわたって水虫が広がっている場合は、飲み薬を使用することがあります。飲み薬は、体の中から白癬菌を殺菌する効果があります。
主な飲み薬の成分としては、以下のものがあります。
- イトラコナゾール
- テルビナフィン
- ネイリン
飲み薬は、副作用が出る可能性もあるため、医師の指示に従って服用することが重要です。また、妊娠中や授乳中の方は、服用できない場合があります。
花小金井駅前スキンクリニックでは、患者様一人ひとりの症状に合わせた適切な薬剤を選択し、治療を行います。水虫でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。