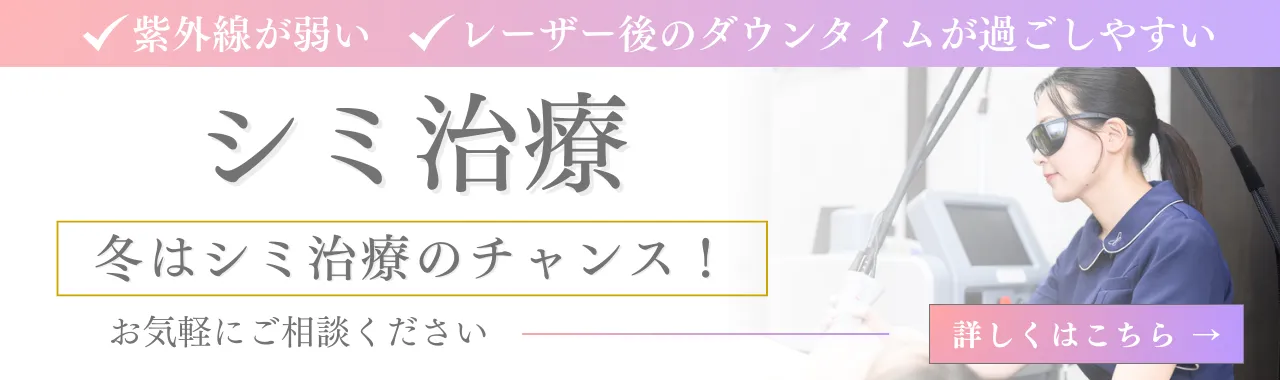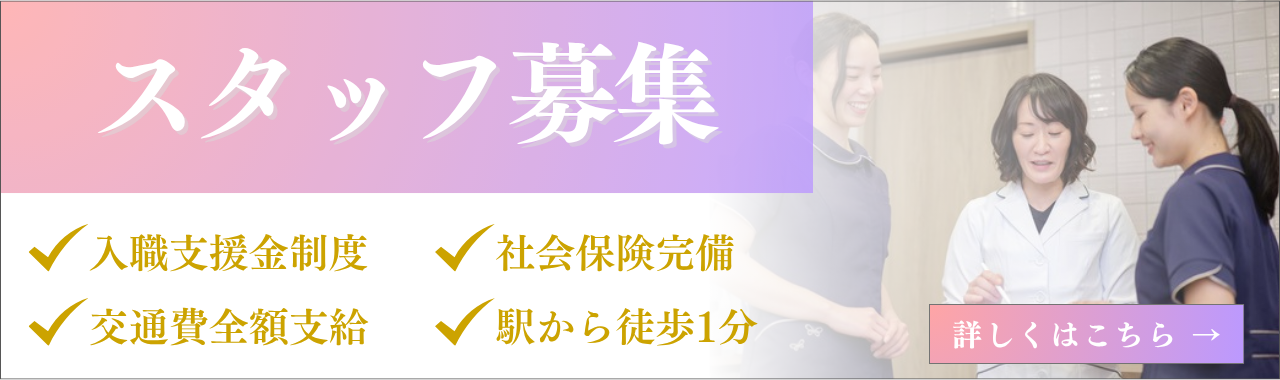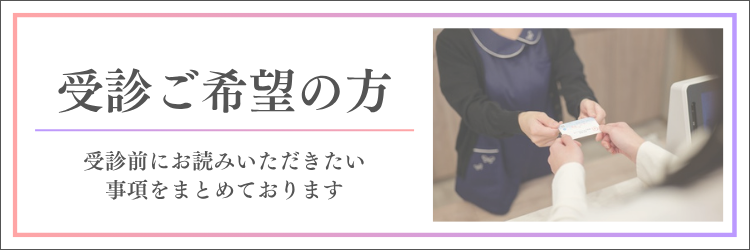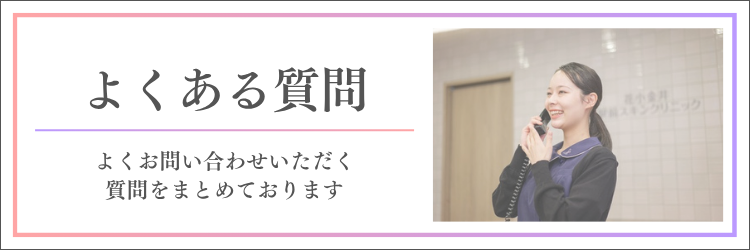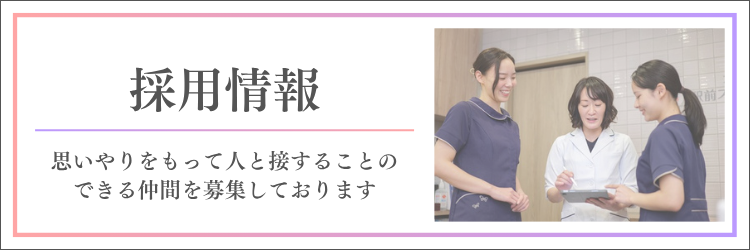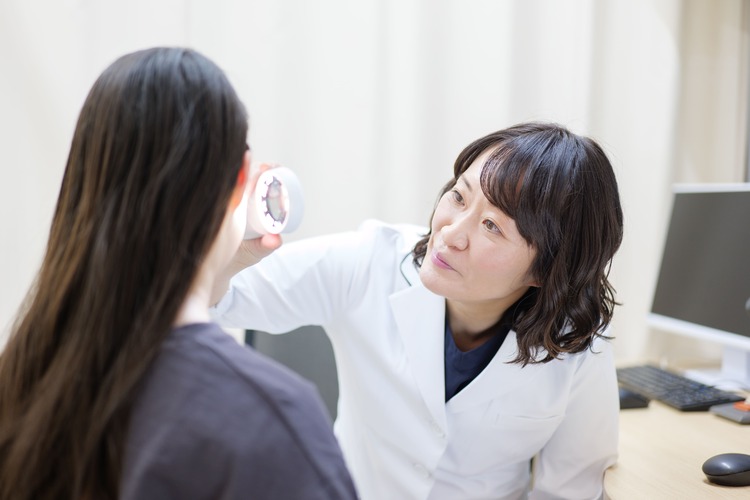
当院は、お子様(赤ちゃん)からご受診可能です。お子様の皮膚の異常や気になる症状がある際は、お気軽にご相談ください。
発熱や腹痛、下痢など、皮膚科以外の症状がある場合は、小児科をご受診いただきますようお願いいたします。
小児皮膚科について
お子様の皮膚トラブルもご相談ください。お子様の皮膚トラブルも、大人と同じように様々ありますが、ご相談が多い症状としては、乾燥によるかゆみ、あせも、アトピー性皮膚炎、イボ、少し大きくなってくるとニキビのご相談も増えてきます。
赤ちゃんのよだれかぶれやおむつかぶれ、乳児湿疹なども、わかっていても症状が強くでると親御さんはとても不安になるかと思います。お気軽にご相談ください。
イボ治療も、とても多いご相談です。一番よくないのは、「痛いから」「怖いから」症状があっても受診できず、広がったり増えたりすることです。当院では、痛みの少ない治療、怖くない治療を心がけております。
当院では乳児、小児のあざのレーザー治療も行っています。
異所性蒙古斑、太田母斑、扁平母斑など、レーザーの適応かどうか、まずは診察にお越しください。
※あざが広範囲にわたり全身麻酔の必要がある場合や、お子さまでじっとしていられず暴れてしまうなど患者様に危険がある場合には、総合病院にご紹介させていただきます。
小児皮膚科の対象となる主な疾患
乳児湿疹
1歳ごろまでの乳児に起こる湿疹をまとめて乳児湿疹とよびます。
乳児湿疹の典型的な症状は、口周り、首、手や足の関節部に赤みやカサカサ、ぶつぶつができます。程度の軽いものは、こまめに優しく汚れや汗などを拭き、保湿をすることでよくなっていきます。症状が強いときは、弱いステロイドを短期間使って治療します。ただれた状態が長く続くと、アトピー性皮膚炎を起こすリスクが高くなるといわれていますので、適切にステロイドを使い、良い状態に治療してから、保湿で維持することが目標となります。
スキンケアの方法から、今の状態は果たして薬が必要なのか正常な範囲なのかといったご相談まで、悩まず早めに受診していただきたいと思っています。
おむつかぶれ
尿や便などが刺激となり、おむつが当たり、むれる部位に赤いブツブツやただれが生じます。おしっこに含まれるアンモニアの刺激や、密閉されたことで細菌や皮膚を刺激する物質が増えることが原因といわれていますので、できるだけおむつをこまめに替えて、清潔と乾燥を保つようにするのが理想です。
おむつを替えるときは、市販のおしり拭きシートや、肌の敏感な状態のときはガーゼをぬるま湯で絞ったもので優しく抑えるように拭き、少し時間をおいて乾かしてからおむつをつけるのが良いです。きれいにしようと一生懸命こするのは逆効果ですので、おさえるようにふいてください。
気をつけていても、下痢を繰り返すときや体調によっては、おむつかぶれは起こりますので、ご不安なときは早めにご相談ください。
治療は、ステロイドの塗り薬や、亜鉛華軟膏などの保湿でよくなることが多いです。
ですが、おむつかぶれに似た症状で、同じように蒸れた環境で起こりやすい「皮膚カンジダ症」があります。カンジダ症の場合、ステロイドが効きませんので、顕微鏡の検査をして診断がついたら、抗真菌薬の塗り薬をお出しします。
小児(子ども)のアトピー性皮膚炎
アトピー性皮膚炎は、乳幼児期(生後2か月から2~4歳)に発症することがおおいです。
遺伝的な要素・皮膚のバリア機能が弱くなることなどを背景に発症します。多くは、年齢が上がるにしたがって、軽症化し、治癒していきますが、一部成人まで症状が続く場合もあります。
アトピー性皮膚炎の診断基準は、
- かゆみを伴う湿疹がある
- 左右対称・関節部などの好発部位に特徴的な分布を示す
- 慢性的に繰り返す
以上3つの項目を満たすとアトピー性皮膚炎と診断します。
アトピー性皮膚炎の治療の目標は、適切な塗り薬の使用により、日常生活に支障がでない肌の状態を維持することになります。
良くなったから、まったく保湿もしなくて良くなるというのは言い過ぎで、保湿をすることを生活習慣としていただくことにより、かゆみのない快適な状態を長く維持することが大切になります。
お子様の場合、ご両親が塗り薬を塗りますので、精神的にもご両親が悩まれることも多く見受けられます。ご家庭で悩まずに、ぜひクリニックで相談してください。
イボ(尋常性疣贅)
イボは、主に手の指、足裏に多く見られる、カサカサした硬いできものです。黒く小さな点が中に見えたり、盛り上がってくることもあります。ヒトパピローマウイルスの感染によるもので、放っておくと大きくなったり、増えてきます。気になるできものができたときは、早めにご相談ください。
イボの治療は、イボの診療ガイドラインで「液体窒素」がすすめられています。液体窒素でイボを凍らせ、低温やけどの状態にしてはがしていきます。この方法が最も一般的で効果の認められている方法になります。当院ではスプレータイプの液体窒素を使用し、押し当てずに短時間の治療で終わらせることが可能です。
しかし、液体窒素は痛みがあり、お子様にとっては辛い治療でもあります。液体窒素を必要最低限にとどめて、塗り薬や貼り薬をお出しすることもあります。痛みの少ない治療をご希望の方はお申し出ください。
水いぼ(伝染性軟属腫)
水いぼは、伝染性軟属腫ウイルスの感染により、小児によく発症します。特に夏に多く見られます。お顔をも含めて体のどこにでもできる、ドーム状に盛り上がった小さなできものです。掻くことで、周囲に増えていきますが、通常、半年から2年ほどで免疫がついて自然になくなることがほとんどです。
そのまま放っておいてもよくなるのですが、接触するとうつるため、学校や水泳教室などで、水いぼを取ってくるように言われることがありますので、その際は、麻酔のシールを事前に貼ってからピンセットで取る処置をクリニックで行います。
痛みにより、クリニックが怖くなってしまうことも多いので、無理にとる必要はないと考えていますが、ご希望があれば痛みを軽減する麻酔テープを使用して、処置をさせていただきますのでご相談ください。
とびひ(伝染性膿痂疹)
夏に多くなる、お子様に多い皮膚の病気です。虫刺されやアトピー性皮膚炎、あせもなどのかゆみのある湿疹を掻いてしまい傷ができると、細菌が増えることで、じゅくじゅくしたり、水ぶくれ、かさぶたを作って周りに広がっていきます。
細菌が原因なので、かゆみのある湿疹にだされたステロイドの塗り薬を塗り続けてもよくならず広がっていきます。じゅくじゅくしたりかさぶたが増えてくるときは、早めにご受診ください。とびひは、触ることでまわりにうつしてしまうこともありますので、保育園や小学校に行かれるときは、出ている部分はガーゼで保護してあげるとよいでしょう。
治療は、飲み薬や塗り薬の抗生物質を処方します。じゅくじゅくしているところは、きれいに自宅で洗っていただいたり、塗り薬やガーゼで保護する手当をしていただくことで、早く治っていきます。
最近は、抗生物質の効きにくいタイプのとびひも増えており、抗生物質を内服する前に、原因となる細菌をとって培養検査にあらかじめ出しておくことも大切になります。
手足口病
夏に増える感染症で、皮膚の症状が強いため、皮膚科を受診することが多い病気です。発熱は、手足口病の30%で起こりますが、発熱がなく皮膚の症状のみのことも多いです。手のひらや足の裏、口の中に、痛みを伴う赤いぶつぶつや水ぶくれができます。よく効く薬はなく、対症療法のみで自然治癒します。
お口の中の痛みで、水分をとることをがまんしてしまい、脱水になるケースもありますので、水分がとれているか、観察してあげてください。症状がおさまったあと、手や足の皮がむけたり、爪が剥がれたりすることがあります。痛みがでることもありますので、皮膚の症状が強いときはご受診ください。
りんご病(伝染性紅斑)
風邪のような症状がでたあと、1週間ほどあけてから、両ほほが赤くなる特徴的な症状がでます。頬の赤みがでたあと、腕や足、体にもまだらな赤い発疹がでることもあります。特効薬はなく、自然に良くなっていきます。ウイルス感染症ですが、頬に赤みが出るころには感染力はなくなっていますので、登園や登校は制限する必要はありません。
シラミ症(アタマジラミ)
シラミ症は、シラミが人に寄生する病気ですが、お子様で時に集団感染を起こすのが、アタマジラミ症です。
保育園や小学校でうつることが多く、特に夏に多く発生します。頭に白いぶつぶつが見えることがあり、これが虫の卵です。強いかゆみが出ることが多いです。診断は、虫卵が目で見えて診断できることもありますし、顕微鏡の検査で虫の卵を確認して正確に診断することも可能です。
治療は、市販のスミスリンという駆虫効果のあるシャンプーを2週間ほど使います。細かいクシで髪をとかして虫・虫卵を取り除くことも効果的です。
異所性蒙古斑
異所性蒙古斑とは、日本人ではほぼ100%にみられる腰仙骨部(お尻の真ん中あたり)の蒙古斑に対して、それ以外の場所に生じる青色~灰青色のあざです。
ほとんどは、成長とともに5~10歳ごろまでに自然に消えますので治療の必要がないものが多いですが、色調が濃いものは成人まで残ることがあります。
治療は、Qスイッチレーザーまたはピコレーザーによるレーザー治療です。個人差もありますが、3~6カ月毎に3~5回の治療で改善することが多いです。
太田母斑
太田母斑は顔に出現する青あざです。顔の片側の、まぶた、頬、こめかみ、側頭部などに青~褐色の色素班がでます。多くは出生してすぐにはなく、生後1年以内に発症します。思春期以降に出現する場合もあります。
異所性蒙古斑と異なり、自然に消退することはほぼなく、年齢と共に濃くなることも多いため、レーザーの効果がでやすい早めの時期に治療開始することをおすすめします。
治療は、Qスイッチルビーレーザーまたはピコレーザーによるレーザー治療です。
3~6カ月毎に3~5回照射で改善することが多いです。
扁平母斑
生後すぐに現れることが多い、平らで境界がはっきりしている褐色(茶色)のアザです。
3~4個以内であれば、多くの人に見られますが、茶あざが多発する場合、遺伝性の疾患が含まれる場合もありますので、ご相談に来てください。
治療は、Qスイッチルビーレーザーになりますが、治療で薄くなる確率が20~30%程度と低く、また一度消退しても再燃する可能性があり、治療が難しいアザになります。